Q1. 車を買い替えました。自動車共済はどうすればよいですか?
車両入替が可能な用途車種の自動車を新たに取得された場合には、ご契約者本人が車両入替の手続きをすることにより、新たに取得された自動車にご契約を引き継ぐことができますので、すみやかにご契約先のJAにお申込みください。
車両入替が可能な用途車種の自動車を新たに取得された場合には、ご契約者本人が車両入替の手続きをすることにより、新たに取得された自動車にご契約を引き継ぐことができますので、すみやかにご契約先のJAにお申込みください。
以下の内容に変更が生じた場合には、遅滞なくご契約先のJAにご通知ください。ご通知がないと共済金をお支払いできないことがあります。
まず、けがをされた方の救護や事故車の移動などで安全を確保し、警察への届出などを行う必要があります。
1.
相手方の確認
加害事故、被害事故にかかわらず相手方の氏名・住所等を免許証などで可能な限り確認してください。
2.
事故状況・目撃者の確認
事故が起きたときの状況や、衝突位置、信号の色などを忘れないうちに確認してください。また、事故の目撃者がいる場合は、氏名・連絡先などを聞いてください。
3. JAへの事故通知
次のことをお伝えください。
4. 安心サービスの利用
共済期間の中途でご契約のお車を廃車したこと等によりしばらくお車を使用されなくなった場合、一定の条件を満たしていれば、ご契約を一旦中断し、新たなご契約を締結した際に等級を引き継ぐことができる制度がございます。
また、お車の廃車以外でも、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、海外渡航等の理由により、しばらくお車を使用されなくなりご契約を解約する場合でも、同様の制度がございます。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。
レッカー・ロード費用保障条項を締結している場合、ご契約のお車が事故、故障もしくは車両トラブルにより走行不能(自力走行できない状態または法令により走行禁止の状態)となった場合または盗難された場合に、以下のサービス等をご利用いただけます。
1. レッカーサービス
レッカー業者が現場へ急行し、修理工場等までお車を運搬します。
2. ロードサービス
対応業者が現場へ急行し、お車の応急対応を行います。
(例:バッテリー上がり時のジャンピング作業、パンク時のスペアタイヤ交換)
3. 宿泊帰宅等サポート
レッカーサービスをご利用した場合またはお車が盗難された場合に、宿泊施設および公共の交通手段の案内を行うとともに、緊急宿泊(1泊)および公共の交通手段の利用を余儀なくされたために追加的に要した費用(実費)をお支払いします。
4. 陸送等サポート
レッカーサービスをご利用した場合またはお車が盗難された場合に、お車の修理または充電等を終えた後、お車を引き取るために要した以下のいずれかの費用(実費)をお支払いします。
5. 燃料給油サービス
お車が燃料切れにより走行不能となった場合、対応業者が急行し、お車にガソリン(レギュラー、ハイオク)または軽油を最大10ℓまで提供します。
● ご利用にあたっては、事前にJA共済サポートセンターにご連絡(JAまたはJA共済事故受付センターを経由する連絡を含みます)ください。
● 本サービスの費用は、レッカー・ロード費用保障条項の支払対象となる場合、当該条項の共済金のお支払いとして取り扱います。
● 本サービスをご利用いただくにあたっての詳しい内容、注意事項等は、「レッカー・ロードサービス利用規約」をご参照ください。
継続後の共済掛金が高くなる場合はいくつかありますが、その1つに「型式別掛金クラス制度」があります。
「型式別掛金クラス制度」は、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車および自家用軽乗用車について「型式」(注記1)ごとの事故実績によって担保ごと(「車両・車両諸費用(代車費用のみ)」「対人」「対物」「人身傷害・傷害定額」)に17クラス(自家用軽乗用車は7クラス(注記2))に区分し、それが共済掛金に反映される制度です。共済掛金はクラス1が最も低く、クラス17(自家用軽乗用車はクラス7)が最も高くなります。
〇自家用普通乗用車、自家用小型乗用車
〇自家用軽乗用車(共済期間の初日が令和7年1月1日以降のご契約)
| 車両 (注記1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 対物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 傷害 (注記2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 掛金 | 低 ← → 高低 ← → 高 | ||||||
この掛金クラスは、現在位置付けられているクラスが妥当であるかを毎年検証してクラスの見直しを行っており、その結果は毎年1月から適用されます。したがって、ご契約者自身が事故を起こされていなくても、その型式自体の事故実績が高い場合、昨年と同様の契約条件であっても継続後の共済掛金が高くなるといったことが発生いたします。
その他、主に以下のような場合に継続後の共済掛金が高くなることがあります。
万一、終期日以降に継続の手続きをされる場合でも、前契約の終期日の翌日より7日以内に継続契約をご契約いただければ、割引等級を継承することができます。
ただし、終期日以降継続の手続きをなされるまでの期間は未保障となります。
なお、一定の条件を満たしている場合に限り、共済期間の末日の翌日以後1か月以内にご契約のお手続きをしていただくことにより共済期日の末日から同一の内容で継続されたものとしてお取扱いできる場合もあります。また、一定の条件を満たしている場合に限り、前契約の終期日の翌日より180日以内にご契約のお手続きをしていただくことにより、割引等級を継承できる場合もあります。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。
共済期間の途中に運転者の年齢条件を変更することも、ご契約の継続の際に運転者の年齢条件を変更することも可能です。ご契約先のJAにお申込みください。
別居のお子様に変更される場合は、原則、割引等級は引き継がれません。記名被共済者が個人の場合は、引き継げるのは次の範囲です。詳細はご契約先のJAまでお問い合わせください。
自動車共済では、業務使用、通勤・通学使用、日常・レジャー使用といったご契約のお車の使用目的を問わず、その他の所定の条件を満たす場合には共済金をお支払いいたします。
別居の既婚のお子様は、運転者家族限定特約でいう「家族」には該当しませんので、お支払いの対象にはなりません。
この特約でいう「家族」とは次のいずれかに該当する方をいいます。
家族原動機付自転車賠償損害特約については、自動車共済に運転者一定年齢限定保障特約が付加されていても、運転される方の年齢に関わらず保障されます。
自動車共済に日常生活賠償責任特約を付加いただくことで、自転車で走行中の事故により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保障いたします。
自動車共済の弁護士費用保障特約については、「自動車に起因する事故」によって被った身体・財物の損害について、被共済者が相手方に法律上の損害賠償請求を行う場合に、相手方との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用(着手金、報酬金等)を保障する特約になります。なお、お車を複数台お持ちの場合は、それぞれのお車を自動車共済にご加入いただき、ご契約ごとに弁護士費用保障特約の付加が必要となります(1台のご契約に弁護士費用保障特約を付加することで、所有または常時使用される他のお車を保障できるものではありません)。
自動車共済の日常生活事故弁護士費用保障特約については、「日常生活に起因する事故」(注記)によって被った身体・財物の損害について、被共済者が相手方に法律上の損害賠償請求を行う場合に、相手方との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用(着手金、報酬金等)を保障する特約になります。なお、お車を複数台お持ちの場合は、そのうちの1台のご契約に日常生活事故弁護士費用保障特約を付加いただくことで1世帯(同居の親族等)を保障いたします。
ご契約者(被共済者)さまのほうに責任のある事故(特に人身事故)の場合、相手方へのおわび・お見舞いや、葬儀への参列などを通じ、相手方に十分誠意を尽くすことが円満な事故解決への第一歩となります。
(ポイント)
JAにご相談なく賠償のお約束や示談をされますと、共済金で全額保障できなくなることもございます。相手方から金銭に関する要望があった場合は、必ず事前にJAの事故担当者にご相談ください。
物損事故・人身事故にかかわらず、必ず警察への届出をお願いいたします。警察に届けることによって事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことにつながります。なお、警察への届出は、法律(道路交通法第72条)によって定められた義務でもあります。
損傷されたお車は修理工場に入庫いただいても結構です。ただし、お車の損害を確認させていただきますので、JA自動車共済に加入している旨を工場担当者の方にお伝えください。
過失(責任)割合の決定にあたり、まずは事故当事者の方からお聞きした情報や道路状況等をもとに、事故の事実関係を明確にしていきます。
そのうえで、道路交通法に定められた優先関係・遵守事項、その他交通ルールの違反の有無・程度、過去の裁判例などから妥当な割合が決められていきます。
「割増・割引等級制度」とは、事故の有無や件数等を、継続されるご契約の共済掛金に反映させる制度です。共済金をお支払いする事故の有無・種類、事故件数等により、継続後のご契約の等級(1から20等級)および事故有係数適用期間(「0年」から「6年」)(注記1)が決定されます。
≪初めてご契約される場合≫
初めてご契約される場合は6等級(注記2)となり、また、事故有係数適用期間は「0年」となります。
≪継続してご契約される場合(他社からの継続を含みます。)≫
共済期間の初日がいつであるかにより、継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定方法が異なります。詳しくはご契約先のJAまでお問い合わせください。
事故を起こして共済金が支払われた場合、原則として、次回ご契約時の等級は3等級下がり、共済掛金が上がります。(注記1)
一方、事故を起こしても結果的に共済金が支払われなかった場合(「事故を起こしてJAに連絡したが共済金を請求しなかった場合」、「共済金を請求したが共済金の支払いに該当しなかった場合」等)は次回ご契約時に等級が下がることはありません。(注記2)
なお、次回継続する際の共済掛金を試算することもできますので、JAの事故担当者にご相談ください。
ご加入先のJAが営業時間外の場合は、フリーダイヤルの事故受付センター(電話:0120-258-931)にご連絡ください。お客さまのご要望により、初期対応専任のスタッフがご契約者や事故の相手方と連絡を取り、修理工場への連絡等必要な対応を迅速に行います。
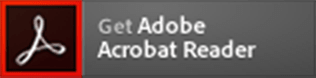
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader®が必要です。
Adobe Reader をダウンロード